自分で決める力を育てるために
- hysbrmk114
- 6月9日
- 読了時間: 3分
学生時代の私
学生時代の私は、将来どんな仕事に就きたいのか、はっきりとしたイメージを持てずにいました。「公務員か、自動車工場か、どこかでパソコンを使う仕事くらいしか思いつかない」そんなふうに思い悩んでいたのです。
母の言葉で気づいたこと
当時は成績もあまり良くなく、体力にも自信がなかったため、「自分に何ができるんだろう」と不安ばかりが募っていました。そんなとき、母がかけてくれた言葉があります。「他の普通の人と比べて弱いから、体力的に負担が少なくて、座ってできる仕事を考えてみたらどう?」そのひと言が、パソコンを使う仕事に目を向けるきっかけになりました。
思い返せば、小学6年生の頃から、自宅でパソコンを使ってホームページを作ったり、ブログを更新したりしていました。その経験が、今の自分の方向性につながっているのだと思います。
自分で自分のことを決める
そして今、私は感じていることがあります。特に聴覚に障がいのある子どもたちにとって、「自分のことを自分で決める力」を育てることは、とても大切だということです。
社会に出ると、聞こえない人特にろう者が自分で選択する力を育む機会が少ないことに気づかされます。実際、聞こえない子どもたちは「自分で選ぶ」という経験があまりない場合も多く、大人になったときに「どう決めたらいいのか分からない」と戸惑うことがあります。
「自分で決められない」「知的障がいがあるのでは」と思われることもあるかもしれません。でも実際は、「決める練習」をする機会がなかっただけ、ということがほとんどです。
私自身、不安になることもあります。けれど、不安だけでは前には進めません。子ども時代というのは、もともと家族や学校といった、限られた世界の中で過ごすものです。
さらに、聞こえない子どもたちは、周囲の会話が自然に耳に入るわけではありません。「先生と誰かが話している内容」や「友達同士のちょっとした冗談」など、日常の中にあふれる細かな情報に気づきにくいことがあります。
チャンスを活かす
そのため、何気ない会話から学ぶチャンスや、自分の気持ちを伝える機会が少なくなってしまうこともあるのです。だからこそ、限られた環境の中で、どんなふうに「自分の声を出せる場」を持てるかが、とても大切だと感じています。
聞こえる人たちは、日常の中で自然と情報を得て、意思決定力を育てています。一方で、聞こえない子どもたちは、情報に触れる機会が限られがちで、それが判断力や意思決定力の育ち方にも影響するのです。
だからこそ、幼い頃からさまざまな情報に触れ、自分で考え、選ぶという経験を少しずつ積んでいくことが大切だと私は思っています。もちろん、危険を避けるために、大人のサポートが必要な場面もあります。けれど、「あなたには無理」と最初から可能性を決めつけてしまうことは、その子の未来を狭めてしまうかもしれません。
自分らしさを伸ばそう
子どもたちは、それぞれの環境の中で育っていきます。その中で、「どうやって自分らしさを伸ばしていけるか」が、大きな成長につながると感じています。
いま、何かに迷っていたり、自分で決めることが難しいと感じている方がいらっしゃるなら──その気持ちを整理しながら、「自分が本当に望んでいる未来」について、一緒に考えてみませんか?
私自身も、これまでの経験を通じて、コミュニケーションを大切にしながらサポートをさせていただいています。もし、「自分で決める力を育てていきたい」「迷いを整理したい」と思われたなら、コーチングという方法を試してみるのもひとつの選択肢かもしれません。必要な時は、ぜひ当事者の未来コーチにお気軽にご相談ください。


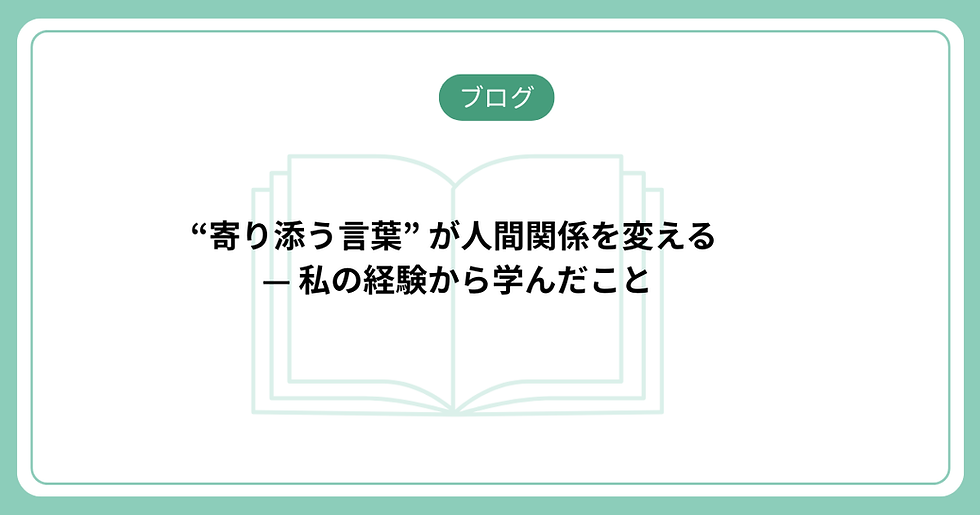
コメント